 |
| 世界遺産・高野山 |
今年も涼を求めて、兄弟4人で高野山に行った。
 |
 |
. . |
 |
. . |
 |
| 観音像と井戸 |
ここに小さな椅子が 運ばれてくる。 |
あらかじめ宿坊で精進料理を予約してあったので、バスで小田原通り下車すぐの大圓院(大円院)へ。
ここは平家物語の維盛高野の巻にある「滝口入道と横笛」の恋にまつわる伝説のあるところ。
平家の武将・滝口時頼が身分違いで添われぬ雑仕の横笛への思いを断ち切るために、出家しやがて高野山で修行する。横笛も後を追って尼になるが、病を得て(一説では川に身を投げて)亡くなる。その後高野山の滝口入道の下へ一羽の鶯が飛んできて美しく囀った後井戸に落ちて死んでしまった。入道にはこの鶯が横笛であることが分かり、ねんごろに葬ったというのだ。当院にはその井戸が残されていて供養の観音像が立てられている。
精進料理は一つ一つおいしく味付けられたいるのだが、こんな場合、和食の通例で全体として塩分が多い。家でも応用できそうな親しみのある料理であった。この味には鰹やだしじゃこはつかわれていないのだろうか。私と義妹が正座できない旨伝えてあったのでお膳を重ねてうまい具合に椅子席を設えてくださった。
近くの石堂丸の説話で有名な刈萱堂に入った。お堂の内部を一周するとお話がすべて分かるようになっている。
 |
. , |  |
バスで奥の院へ向かう。杉並木の中に歴史上有名な人々のお墓がたくさんある。
 |
. . |  |
| 豊臣家 徳川幕府への遠慮からだろうか、個人名は見当たらずささやかな石塔があるのみ。 |
織田信長と筒井順慶が 並んでいるのも面白い |
|
 |
 |
|
| 家康の次男・結城秀康石塔(重要文化財) |
名も知らぬ人々の石碑で築かれたピラミッド 享保年間のものもあった |
 |
奥の院は撮影禁止。脱帽。 この一番奥に弘法大師がまだ生きておられるという信仰である。 橋の手前から撮影した。 橋は美しいせせらぎ「玉川」に掛かっている。 お遍路さんの衣装を身につけた人が大勢参拝して、 弘法大師の御廟の前でお経を唱え、立ち去るときあいさつしていかれた。 そのほかツアーのための案内人が面白おかしくしゃべっていたが、 ちょっと聞いたら、人を見下すような感じがする人があった。 毎日大勢の人がうなづきながら、自分にとってはなんでもない話を 聞いてくれると、思い上がりが出てくるのかも知れない。 |
 |
たくさんのお墓や お地蔵さんに供えられている 「こうやまき」 お墓の管理をしている人に 尋ねて教えてもらった。 |
高野山全体が行政上、高野山町になっていて、うろ覚えだが人口は5万ぐらいあるらしい。到着早々には、モミジマークの車の事故現場もバスの窓から見た。バスは800円で一日乗り降り自由。とても便利である。
そのバスを利用して、さらに金剛峰寺や根本大塔など見学する。この辺りで気がついたのだが、内陣に参詣しなかったからかここまで参詣料は全く要らなかった。
 |
 |
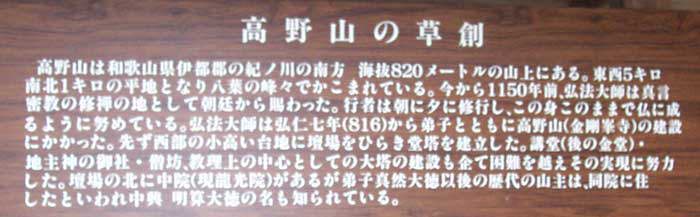 |
 |
| 趣きのある不動堂(?) |
 |
| 根本大塔(縦2枚合成パノラマ) |
大急ぎで麩善という麩専門店へ走り、お土産に「あんぷ」(餡麩)とモミジ麩、手まり麩を購入し、バスの時間を見ると、ちょうど大門へ先にいけるので、また急いだ。
 |
 |
夕暮れ迫る山の上、女人堂を窓から見ながらバスでケーブル乗り場へ回り、難波へ帰り着いたのは午後8時だった。